逆手に構えた笛。そこに隠された心根とは・・・

私は笛吹き
篠笛(しのぶえ)と能管(のうかん)を吹いています
皆さま、こんにちは。日本の横笛奏者、福原寛と申します。
まずは自己紹介を兼ねて、私が吹いている笛について少しだけご紹介しましょう。
日本の横笛といいましてもいろいろと種類がありますが、私が何を吹いているのかと申しますと、「篠笛(しのぶえ)」と「能管(のうかん)」です。主に、歌舞伎音楽(歌舞伎で場面や心情を表現する伴奏音楽として発達してきた音楽)などの三味線音楽に合わせて演奏します。

▲上の3本が篠笛、黒い笛が能管です
篠笛(しのぶえ)について
篠笛はとてもシンプルな楽器で、篠竹(女竹)に息を入れる孔と指を乗せる孔を七つ開けただけの作りです。唄うようにメロディーを吹きます。
祭囃子などでも使われる楽器なので、馴染みのある方も多いのではないでしょうか。
能管(のうかん)について
能管はちょっと不思議な横笛です。見た目は龍笛(りゅうてき・雅楽で使われる竹笛。幅広い音域を持つ音色から「天に昇る龍の鳴き声」と例えられたのが名前の由来と言われている)とほぼ同じですが、内径(ないけい・笛の内部のこと。微妙な違いで音が変化する)がとても変っていて雑味の多い音が出ます。
篠笛とちがって、唄うのではなく、「語る」ような演奏をします。メロディーを吹くというのとはちょっと違う、独特の音色です。
世界共通!?横笛の構え方
さて、横笛は世界中に存在する楽器の一つですね!皆さんがよく見るのは西洋楽器のフルートやピッコロでしょうか。
と、突然ですが、皆さん、ちょっと笛を構えるしぐさをしてみてください。あっ、周りに人がいる場合は、笛を構えるイメージだけで大丈夫ですよ笑
さあ、皆さん、自分の体の右側、左側、どちらに笛を構えましたか?? ほとんどの方は、自分の体の右側に笛を構えられたかと思います。
私も最初に笛を始めた時、なんの疑いもなく右肩の方へ笛を構えましたが、ある時ふっと、「なぜ右に構えるのだろうか」と疑問を抱きました。逆に左肩の方へ構える国は無いものかと…
無いですね!
先ほど言ったフルートやピッコロなどの西洋楽器は勿論、インドのバンスリー、中国や韓国など他のアジア圏の横笛も同じく、右へ構えます。
これは人間だけではなく、神様も同じです。
 ▲インドのクリシュナ(スリ・マリアマン寺院)(By AngMoKio – 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14642480)
▲インドのクリシュナ(スリ・マリアマン寺院)(By AngMoKio – 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14642480)
インドにクリシュナという青いお顔をなさった神様がいらっしゃいますが、右方向へ横笛を持っていらっしゃいます。日本でも薬師寺五重塔のてっぺんにいらっしゃる水煙の飛天(天女)も右側に。
左に構える横笛、その心根とは・・・
しかし、私は体の左側、つまり逆手(さかて)に笛を構えるプロの横笛演奏家に、一度お会いしたことがあります。インドのハリプラサード・チャウラスィアーという凄い笛吹きなのですが、左に構えていらっしゃいました。
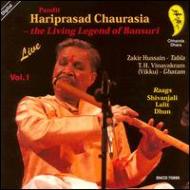 ▲Living Legend Of Bansuri(Hariprasad Chaurasia:ハリプラサードチョウラシア)
▲Living Legend Of Bansuri(Hariprasad Chaurasia:ハリプラサードチョウラシア)
本来は右に構える笛のはずなのに、何故逆に構えているのか伺ってみますと…
「私はもともと民謡の笛を吹いていて、古典の笛を吹きたくて師の門をたたいたが、許されなかった。民謡の演奏に身を置いたものには教えられないと断わられたのだ。
しかし、私はどうしても師に教えを受けたかった。だから、今までの笛の技術を捨て、初心にもどる決意を表すため、あえて逆手にしたのだ」
と、このような事を仰っていました。インドの厳しい音楽社会にも驚きましたが、それ以上にハリ師の決意と心根に打たれました。
常に初心にかえり、ひたむきに精進する。同じ、終わりのない芸の道に精進する一人として、見習うべき心だと強く感じました。
横笛はとてもシンプルな楽器ですが、演奏者の息を使って奏でるため、人間性や感情、精神状態などがそのまま伝わってしまう、素直で奥深い楽器でもあります。ぜひその面白さを、皆さんも味わってみてください!




和ものびとでは、今後も日本の伝統文化・芸能の担い手から様々な情報をお届けします。更新情報はSNSで随時お届けしてまいりますので、日本文化がお好きな方、和ものについて興味をお持ちの方は、ぜひ下記よりフォロー・登録をお願いいたします。
また、周りの方への口コミでのご紹介も大歓迎です!
リンクフリーですので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。